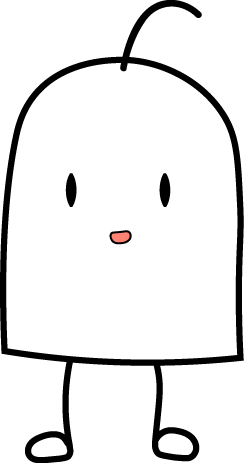
電子技術科(都留キャンパス) No.493
📅令和7年9月1日(金)
今回は、電子技術科(都留キャンパス)2年生の授業『制御工学』の様子を紹介します。
この授業では、機械の動作を決められた順序で制御する「PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)」のプログラム設計方法を学んでいます。
たとえば、自動販売機の動き――「お金を入れる → 商品を選ぶ → 商品が出る → お釣りが出る」――も、PLCによる順序制御で動いているんです。
今回は、演習問題としてラダープログラムの設計に挑戦!
前回は基本問題(1問目・2問目)に取り組みましたが、今回は少しレベルアップした3問目にチャレンジです!
① モード選択と動作の切り替え
今回の課題は、「モード選択」と「動作の切り替え」。
押しボタンスイッチPB1・PB2で「モード1」「モード2」を選び、PB3・PB4の操作によって、
・モード1ではパイロットランプの点灯・消灯
・モード2ではコンベアの左行/右行を制御します。
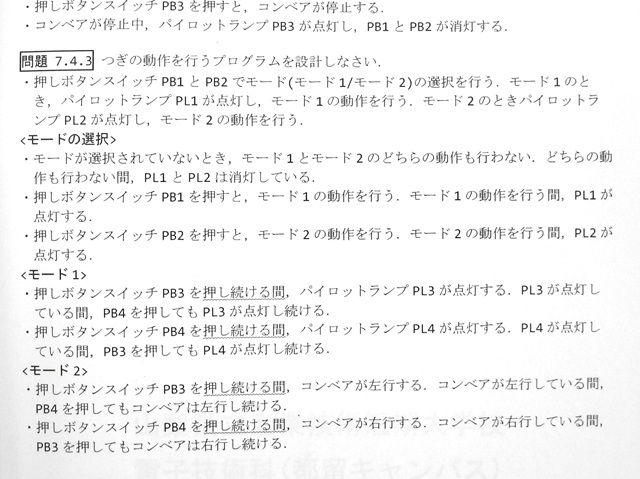
② 『新入力優先回路』って?
モード選択には「新入力優先回路」の考え方が使えそうです。
これは、テレビのチャンネル切り替えなどにも使われる仕組みで、複数の入力のうち“新しく押された方”を優先する動きをする回路です。
…と言っても、実際にはPLCの中でこの“回路”をラダープログラムという“プログラムの形”で作っていきます。
見た目は回路図っぽいけど、ちゃんとしたプログラムなんです。
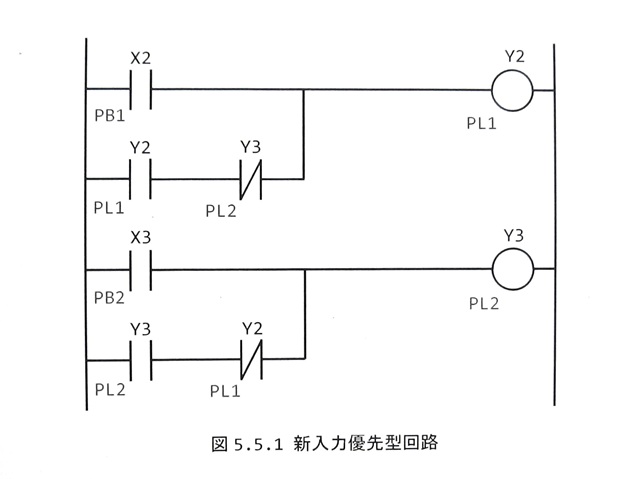
③ ラダープログラムの設計スタート!
さっそく、ラダープログラムの設計に取り掛かります。

④ 手書き図面で構想を練る
完成した図面を見せてもらいました。
まだ「状態遷移図」は未習なので、今回は手書きでラダープログラムを作成。
「プログラム」と言っても、見た目はまるで回路図みたい。
紙の上で、頭の中の動きを整理していく感じです。
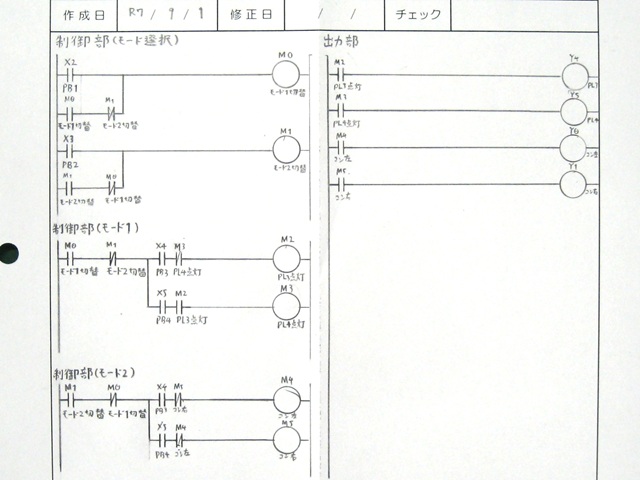
⑤ アプリに入力してみよう
図面が完成したら、専用アプリにラダー回路を入力していきます。
ここからは、いよいよ“プログラムっぽさ”が出てきます。
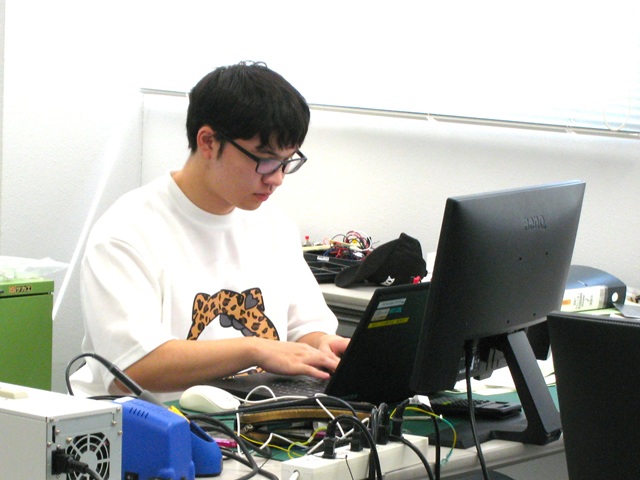
⑥ 入力完了!
こちらが入力したラダープログラム。
線と記号で構成されていて、見慣れるとけっこう面白いんです。
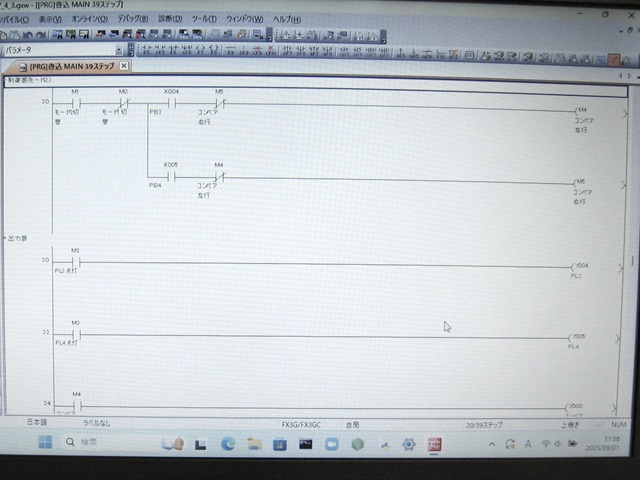
⑦ コンパイルしてPLCへ
ラダープログラムが完成したら、コンパイルして機械語に変換。
その後、PLC本体に書き込みます。
この瞬間、紙の上のアイデアが“実際に動くもの”になるんです。
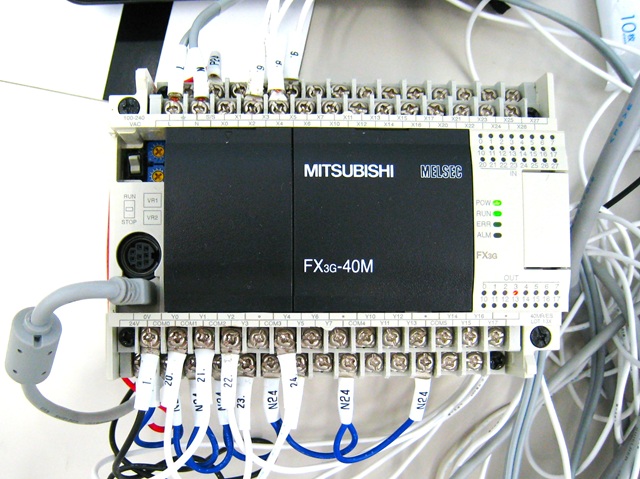
⑧ モード1の動作確認!
モード1を選択してPB3を押すと、パイロットランプ3が点灯。
PB4を押すと、パイロットランプ4が点灯しました。
ちゃんと動いてる…!

⑨ モード2の動作確認!
次にモード2を選択してPB3を押すと、写真では少し分かりづらいですが、コンベアが左側に動き、
PB4を押すと右側に動きました。
動きが切り替わる瞬間、ちょっと感動します。
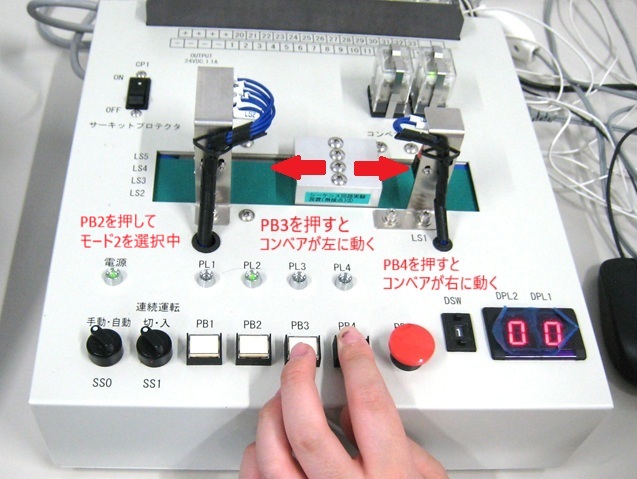
今回もばっちり動作しましたね!
電子技術科(都留キャンパス)では、超小型PC「マイコン」のプログラミングだけでなく、
「PLC」のラダープログラミングについても実践的に学びます。
普通高校でPLCに触れたことがない人も、きっと面白くてハマるはず。
工業高校でPLCに興味を持った人は、さらに進んで「状態遷移図」を使った本格的な設計方法も学べますよ。
📣 次回の授業紹介もお楽しみに